AI・ロボット活用、日本復活の鍵に GMO熊谷氏、KADOKAWA夏野氏、筑波大学・落合氏ら課題と展望語る
2025/9/29 17:48 ジョルダンニュース編集部

2025年9月26日に開催された「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式」で、「革新的リーダーが見るAI・ロボティクス活用の現在と未来」と題したパネルディスカッションが行われた。KADOKAWAの夏野剛社長CEO、筑波大学の落合陽一准教授が登壇し、GMOインターネットグループの熊谷正寿グループ代表をモデレーターに、AIとロボティクスがもたらすビジネスの変革と日本の進むべき道について活発な議論を交わした。

「やりたくない仕事」を代替、AI活用の最前線
まずAI活用の「現在地」について、各氏が自らの現場での取り組みを話した。KADOKAWAの夏野氏は、AIを使って「人がやりたくない仕事をどんどん置き換えている」と表現。具体的な事例として、社内規定に関する問い合わせ対応を生成AIに任せるシステムを挙げた。「産休に入るときの社内手続きは、昔は内規を調べさせていた。今はチャットGPTに聞くと全部答えてくれる。これで人事の担当者の人数が何人か減った」と具体的な成果を語った。
夏野氏は、AI活用の本質は特定のタスクの自動化に留まらないと強調。「AIでこれを成し遂げようというよりは、AIを使って人と人のコミュニケーションを効率化し、新たな発見を促すことで会社全体のプロダクティビティを上げることを目指している」と述べた。
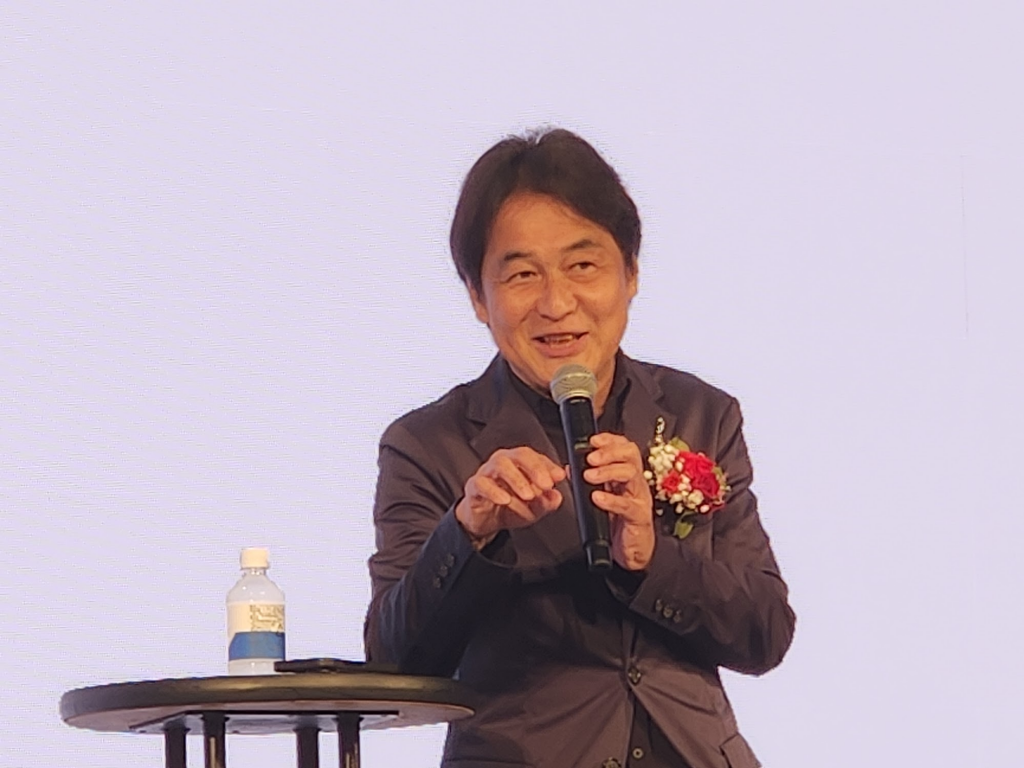
一方、出版業の根幹である物流では、ロボティクスが成果を上げているという。40%にも上っていた書籍の返本率を、物流の効率化と需要予測によって「うちだけ26%まで改善した」実績を示し、AIとロボティクスがそれぞれ独立して進化しているのが日本企業の典型だと分析した。
メディアアーティストであり、大阪・関西万博のプロデューサーも務める落合氏は、クリエイティブの現場がAIによって激変していると語る。万博パビリオンの開発では、「いあままでだと数十人いたような開発チームが、うちの中心メンバーは3人、アプリチームも10人ちょい。すごく少ない小人数で大規模なものを書いている」と、AIが生産性を飛躍的に向上させた実態を明かした。研究活動においても、実験の自動化や膨大な申請書作成にAIは不可欠になっており、「猫の手を借りたい人はAIによって毎日ちょっとずつ楽になっている」と述べた。
炎上防止からDJまで、AIが拓く意外な未来
議論はAIの個人的な活用法にも及んだ。夏野氏は、自身の情報発信におけるユニークなAI活用法を披露し、会場を沸かせた。「最近僕が使うのは、『これ言うと炎上するかな』ってことを一回チャットGPTに聞く。想定される反論を網羅的に出させて、10回ぐらい対話を繰り返すと思考が整理される」と語り、AIを単なる検索エンジンではなく、思考を深める「壁打ち相手」として使うことの有効性を説いた。
マーケティングの未来については、「SEO対策で、AIとAIで対抗し出すと、ロジックの変更をリアルタイムにやり出す。活用しないと一人だけ損することになる」と述べ、AI活用が不可逆的な潮流になるとの見方を示した。

落合氏は、人間の創造性や身体性が問われる領域でのAIの役割に関心を示す。DJを例に挙げ、「酒飲んで盛り上がってるだけの人がDJとして成立するようになるかもしれない」と発言。AIが最適な選曲とミックスを行う一方、人間はフロアを盛り上げるという「指揮者」的な役割に専念する未来像を描いた。これには熊谷氏も「自分が跳ねるとお客さんも跳ねる。ロボットがDJをやった時にお客さんが本当に跳ねるかは研究テーマ」と応じ、AI時代における「人間ならではの価値」がどこにあるのかを問いかけた。
AI大国への道、夏野氏が指摘する「日本の3つの課題」
ディスカッションの核心となったのは、日本が「AI・ロボティクス大国」となるための処方箋だ。GMO熊谷氏が「人類史上最大の産業革命のタイミングに、日本は気づいていないのではないか。2025年は『ヒューマノイド元年』と位置づけ、産学連携でAI・ロボティクス産業を発展させるべきだ。少子高齢化を逆手にとる千載一遇のチャンスだ」と強い危機感と期待感を表明した。

夏野氏はこれを受けて、日本の構造的な問題を3点指摘した。第一に「実証していないビジネス分野に多額の資金を継ぎ込むのがすごく苦手な政府」、第二に「短期的な利益を求め、スタートアップがスケールする前に上場させてしまうVC(ベンチャーキャピタル)」、そして第三に「リスクを取らず安全運転に終始しがちな大企業の経営者」だ。夏野氏は「この3つを解決すべきだ」と断じた。
さらに夏野氏は、AIとロボティクスの最先端がドローンなどの無人兵器開発で進んでいるという厳しい現実を指摘しつつ、日本の活路はクリエイティブ領域にあると提言。「我々がやっている漫画、アニメ、ゲームはすでに5.8兆円産業。これに(AIを)組み合わせると全く違うバリューが生まれる。戦争のツールでは負けるが、平和利用はあり得る」と語った。落合氏も、万博で示したような日本のクリエイティビティと技術の融合が、世界に示すべき一つの方向性だと応じた。
最後に夏野氏は、「AIが仕事を夺う、ロボットが事故を起こすといった恐れが普及を妨げている」と指摘した上で、「一番問題を起こすのは人間。AIやロボットが入ることで今よりマシになる。恐れずに社会にどんどん実装していきましょう」と力強く呼びかけ、ディスカッションを締めくくった。AI・ロボティクスが日本の未来を切り拓く鍵であると同時に、その実現には産官学が一体となった大胆な意識改革と行動が不可欠であることを浮き彫りにした。









