自動運転、日本は世界をリードできる newmo青柳氏、ティアフォー加藤氏らが議論 IVSのセッションで
2025/7/14 15:25 ジョルダンニュース編集部

日本の地域資源、テクノロジー、政策を掛け合わせてモビリティ戦略は「自動運転」で世界をリードできるか
世界で急速に進む自動運転技術の商用化。日本も政府が早期の事業化・実用化を掲げ、その実装は現実味を帯びてきた。特にスタートアップによる技術革新とビジネスモデルの確立が、自動運転社会の実現を加速させている。先日、スタートアップイベント「IVS KYOTO 2025」の中で開催されたセッションでは、日本が今なぜこの分野に本気で取り組むべきなのか、そして地域資源、テクノロジー、政策をいかに掛け合わせてモビリティ戦略を描くべきかについて議論が交わされた。

日本は自動運転において米中に対し遅れをとっているのか?ティアフォー代表取締役CEOの加藤真平氏は、工場内トレーラーや鉱山トラックなど、一般公道を走らない分野ではすでに実用化が進み、日本がシェアを獲得していると指摘する。また、「公共交通、特に路線バスの分野でも日本は強い需要があり、プラットフォーム化が進むことで優位に立てる」と述べた。
一方で、タクシーや自家用車分野では米中が先行していることを認めつつも、「タクシーしかできないわけではない。日本は全てを持っており、全てを接続できるのが強みだ」と強調した。newmo代表取締役の青柳直樹氏も、自動運転タクシーでは米中が先行するが、「AI技術の進化とコストダウンにより、日本もキャッチアップできる可能性が見えてきた」と語る。
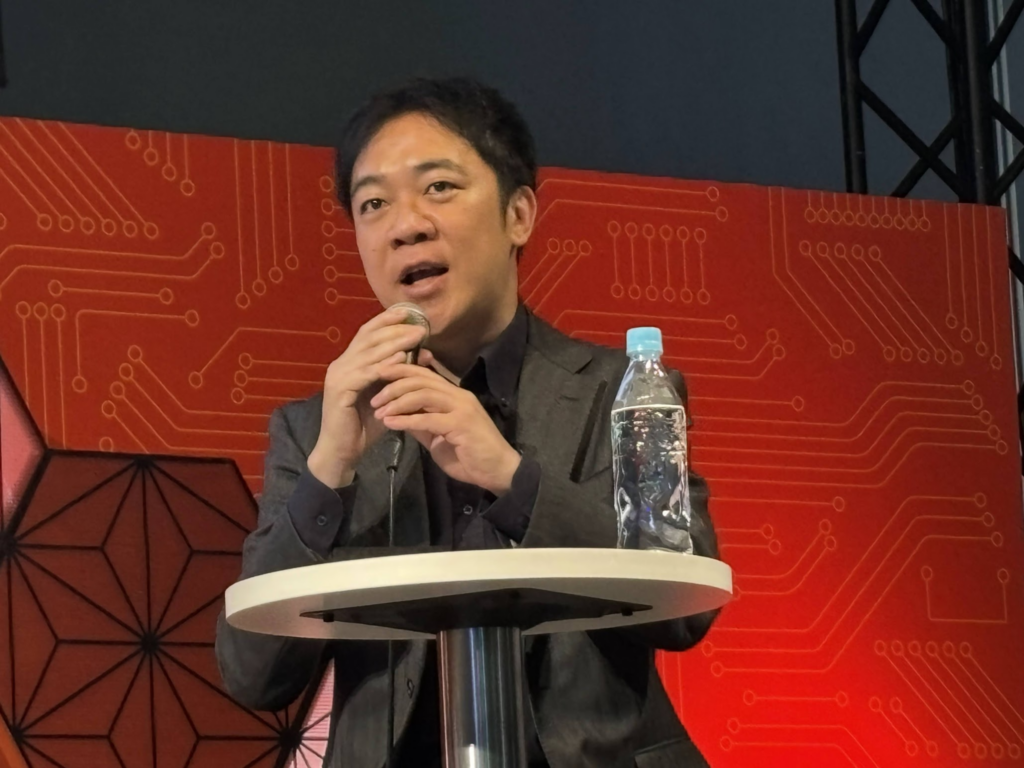
元経済産業大臣の西村康稔氏は、日本が自動運転タクシーで遅れている理由として、安全性に対する規制のあり方と資金力を挙げた。日本の事前規制は時間がかかるが、「一度できるようになれば、当然ヨーロッパでもアジアでもアメリカでも売れるようになる」と西村氏は強調する。また、AIの進化により必要な投資額が大幅に減少している点を指摘。「AIに特化してやればスタートアップでも十分に参入できる」とし、この1〜2年が勝負であり、2〜3年後には米中を上回るものが生まれると期待を寄せた。
経済産業省イノベーション・環境局長の菊川人吾氏も、日本が個々の技術で劣っているわけではなく、社会実装が遅れているだけであり、「政府は今後、全国100箇所で実証実験を拡大する」と述べた。加藤氏は、オープンソースのソフトウェアに取り組んでおり、これが国際標準となり、国土交通省の基準まで取得できれば日本の自動運転技術は圧倒的な強みになるとした。
セッションでは、newmoとティアフォーが7月2日に発表した協業も注目された。青柳氏は、ティアフォーのOS活用により、開発コストを大幅に圧縮できるとし、年内には大阪で自動運転車両を走行させ、2027年には100台規模での運行を目指す。加藤氏は、米中の先行企業が投じた莫大な研究開発費を「ベンチマーク」と捉え、「ウェイモがいかにしてできたのかを分析し、1/10のコストで作ることができれば勝ちだ」と力強く述べた。青柳氏もまた、住民や市民と共に自動運転を作り上げていくことが、日本ならではの確実な方法だと語った。西村氏は、自動運転タクシーのニーズは圧倒的に地方で高く、都市部でのデータ収集と地方での社会課題解決の両輪で進めることの重要性を強調した。
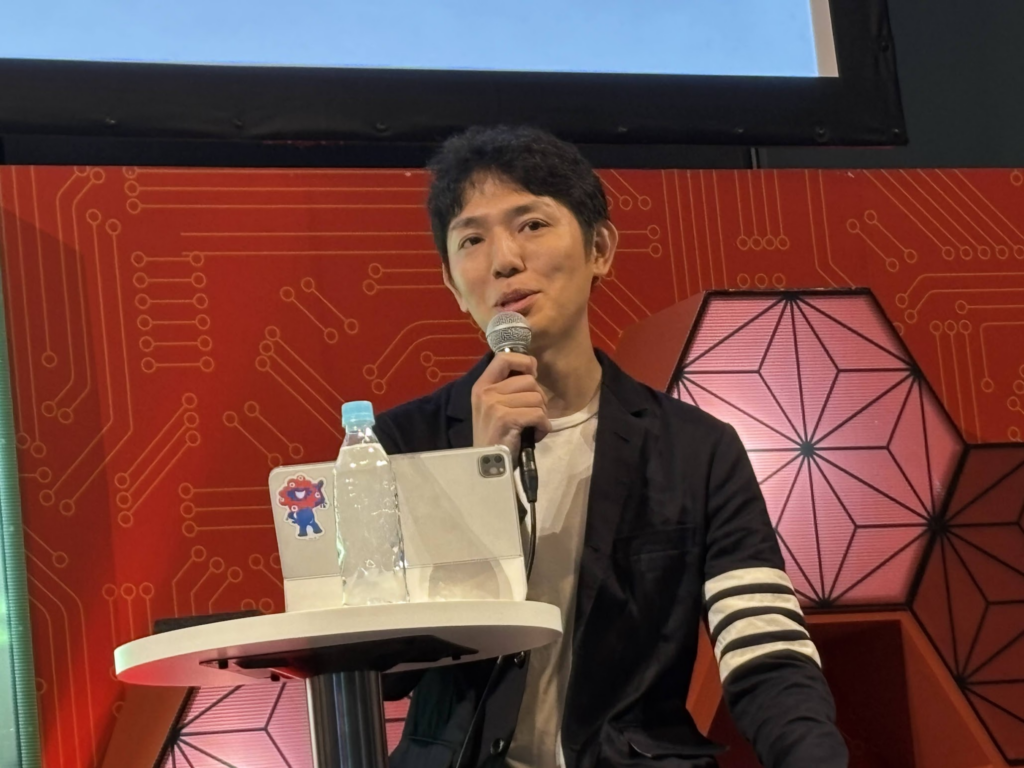
今回のセッションを通じて、日本の自動運転が直面する課題と、それを乗り越えるための具体的な戦略が浮き彫りになった。安全性への徹底したこだわり、オープンソースを活用した効率的な開発、そして多様なプレイヤーが連携する「オールジャパン」体制の構築が、日本の自動運転が世界をリードするための鍵となるだろう。
ジョルダンニュース編集部









