地方分権改革への遅々とした歩み 「希望のコミューン 新・都市の論理」より(7)
2025/2/18 15:19 ジョルダンニュース編集部

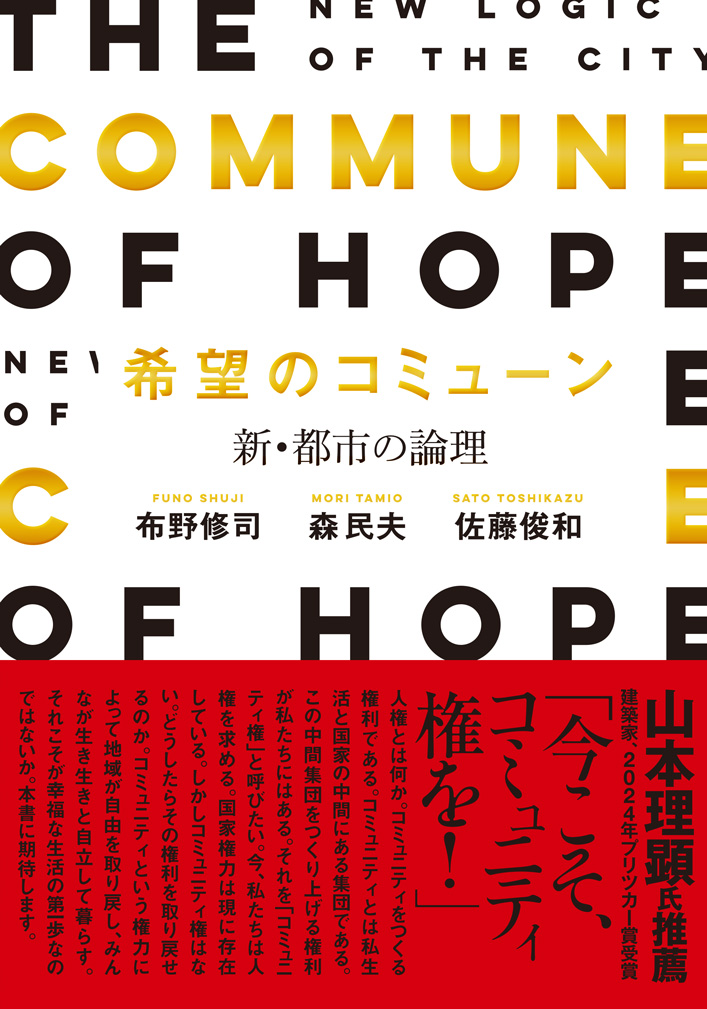
希望のコミューン 新・都市の論理
本記事は2024年9月25日に出版された「希望のコミューン 新・都市の論理(著:布野修司, 森民夫, 佐藤俊和)」の内容を抜粋したものです。
衆参両院による「地方分権の推進に関する決議」
明治維新以来続いてきた中央集権体制に対して、本格的に地方分権改革の必要が公的に宣言されたのは、既に述べたように、1993年6月の衆参両院による「地方分権の推進に関する決議」である。
その決議は、次の通り、東京への一極集中の排除による国土の均衡ある発展という課題を強調している。また、国から地方への権限移譲と地方税財源の充実強化の2点を課題として挙げている。それにより、多様性のある地方公共団体が互いに切磋琢磨し、あるいは、協働しつつ地方の活力を生みだし、東京への一極集中から国土の均衡ある発展を促そうと考えたのではないかと思いたい。
今日、さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除して、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会をつくり上げていくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。
このような国民の期待に応え、国と地方との役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀に向けた時代にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。
したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定をはじめ、抜本的な施策を総力をあげて断行していくべきである。右決議する。
この決議を受けて、翌1994年には、地方6団体により、「地方分権の推進に関する意見書」が提出された。そして、翌々年の1995年に、地方分権推進法が成立するとともに、1999年に、地方分権一括法が成立し、機関委任事務の廃止という改革が行われた。また、2004年からの三位一体改革により、国税である所得税から地方税である住民税への約3兆円の移譲が行われた。
ここまでは、地方分権改革が一歩一歩ではあるが進んでいたという印象がある。しかし、その後の歩みは、国から地方への権限移譲が中心であり、地方税財源の充実強化は遅々として進まなかった。財源はなく権限のみの移譲では当然のことながら真の改革にはつながらない。地方公共団体、特に市町村は財源が伴わない業務のみが増えたと言わざるを得ない。
税財源移譲と三位一体改革
三位一体改革とは、2004年から2006年にかけて実施された「国庫補助負担金の廃止・縮減」「税財源の地方への移譲」「地方交付税の一体的な見直し」を三点セットにした改革のことである。
背景は、小泉内閣による「地方に出来る事は地方に民間に出来る事は民間に」というスローガンの下に、いわゆる小さな政府を目指す動きであった。すなわち、国の財政改革に主眼が置かれていた。そのため、評価は分かれるが、国庫補助事業を削減して地方の創意工夫を促すとともに国から地方への所得税から住民税へのシフトが実施されたことは、我が国においては画期的な出来事であったと思う。具体的には、国税の所得税から地方税の住民税へ約3兆円が移譲された。
その後の地方分権改革は、国から地方自治体への事務・権限の移譲を中心に実施された。2011年から2023年まで13回にわたる「地方分権一括法」が制定され、国から地方公共団体または都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲や、地方公共団体への「義務付け・枠づけ」の緩和等が行われた。その中で特筆できることとして、例えば、農地・農振制度における権限の一部の地方公共団体への移譲などを挙げることができる。
解消されない三割自治
2021年度の国と地方の税財源配分の状況を表した図1によると、一見してわかるように、国民の租税の比率は、国対地方で64:36であり、歳出額の比率は、国対地方が44.1:55.9と逆転している。また、地方歳入決算の内訳は、地方税は全歳入の36.1%にとどまっている。いわゆる三割自治の実態は大きくは変わっていない。
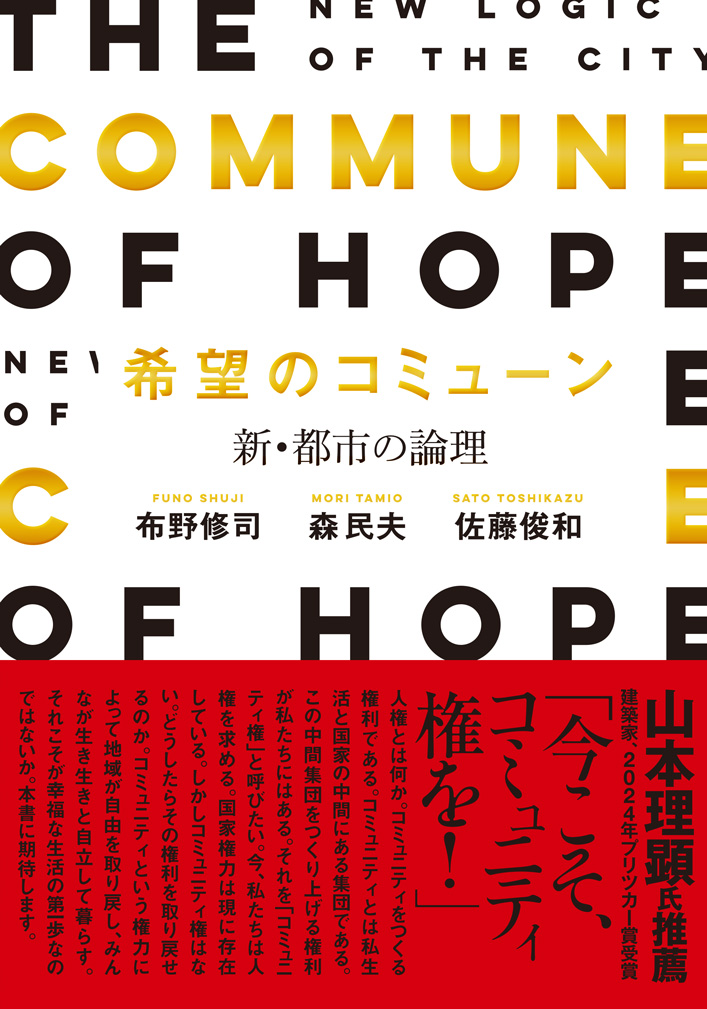
全文を読むには書籍「希望のコミューン 新・都市の論理」をご購入ください。
電子書籍もあります。









